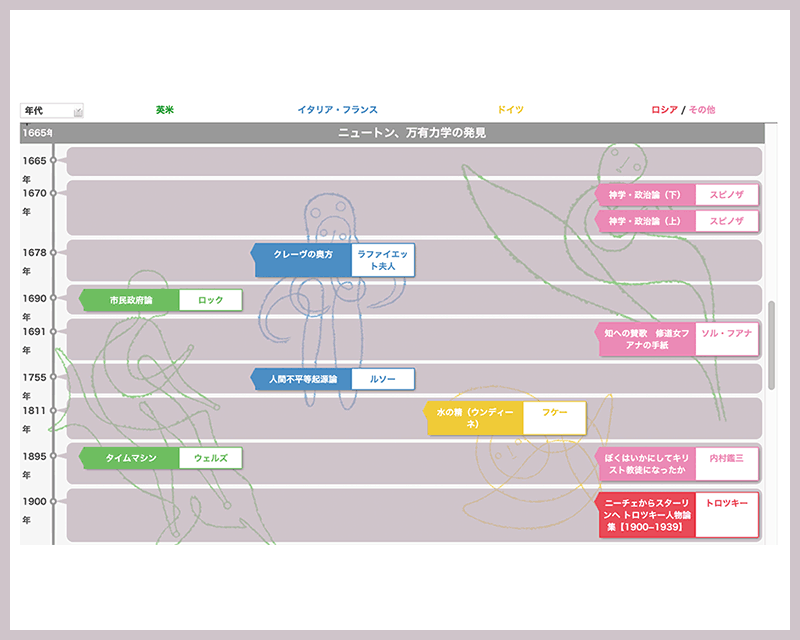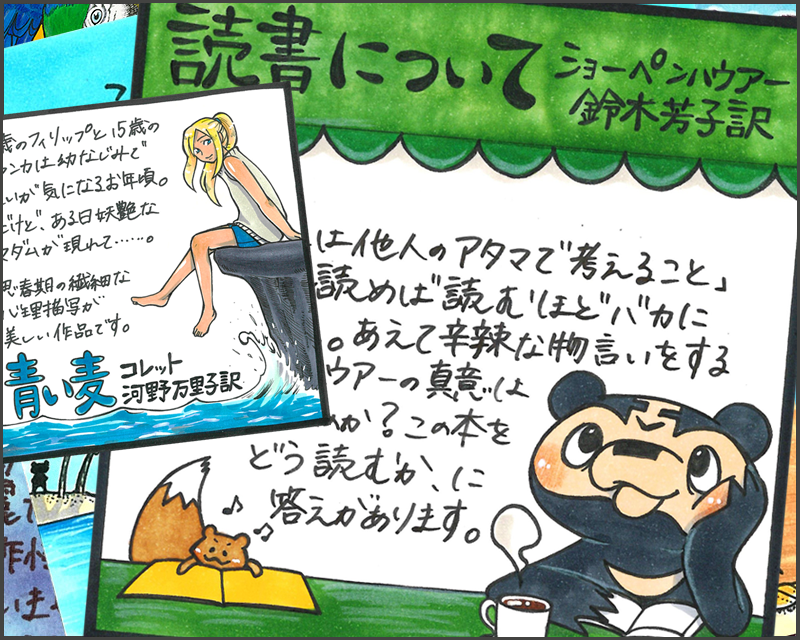高遠弘美さん―産経新聞夕刊(大阪版)連載 第13回「プルーストと暮らす日々」
産経新聞大阪版の夕刊文化欄で連載された(2011年5月〜2012年8月)高遠弘美さん「プルーストと暮らす日々」の第13回です。
プルーストと暮らす日々 13
舟木一夫のヒット曲に「花咲く乙女たち」(一九六四)がある。作曲・遠藤実。作詞・西條八十。西條八十は作詞家として大活躍したほか、詩人として一世を風靡したが、早稲田の仏文科教授を務めた篤実な仏文学者でもあった。
八十は舟木のために書いたこの詞を『失われた時を求めて』第二篇「花咲く乙女たちのかげに」から思いついたという。ただ八十が「街に花咲く乙女たち」と書いた若き乙女たちはプルーストにあっては何より海、それもバルベック(架空のリゾート地)の海を舞台に生き生きと登場する少女たちだった。
すでに第一篇第三章で予告されていたバルベックに、ある年の夏、はじめて祖母と赴いた「私」は、あるとき、堤防を歩く「五、六人の若い娘たち」に出会い、彼女たちが発散する美にたちまち魅了される(第二篇)。
バルベックで描かれるのは、グランドホテルを中心とした社交の場で、海水浴ではない。海は潮風を浴び、ヨット遊びに興ずる場所であっても、社交界の人々が水泳をするところではなかった。少女たちは海を象徴する存在として眼前に現れる。
「ギリシアの海辺で太陽を浴びている彫像のように、海を前にして私が見ていたものは、人間の美の高貴で穏やかな典型ではなかっただろうか」
「私」は少女たちのうち、最初に目が合った「自転車を押して」歩いている少女にとくに心奪われるが、名前もわからない。刻々変わる海のごとく日々変貌してゆく若い娘たちの移ろいやすい美しさをプルーストは余すところなく描きつくす。
「私はその少女たちのすべてを愛しながら、そのうちの誰も愛していなかった。されど、それと知らずに少女たちのことを考えているとき、すなわち、さらに無意識の領域で考えているときには、彼女たちは山のように盛り上がる海の青い波のうねりであり、海を背景にして並ぶ一列のシルエットだった」
やがてその「自転車」の娘の名前が判明する。アルベルチーヌ・シモーネ。その後長く続く語り手の苦しい恋の始まりだった。
(2011年8月4日 産経新聞(大阪版)夕刊掲載)