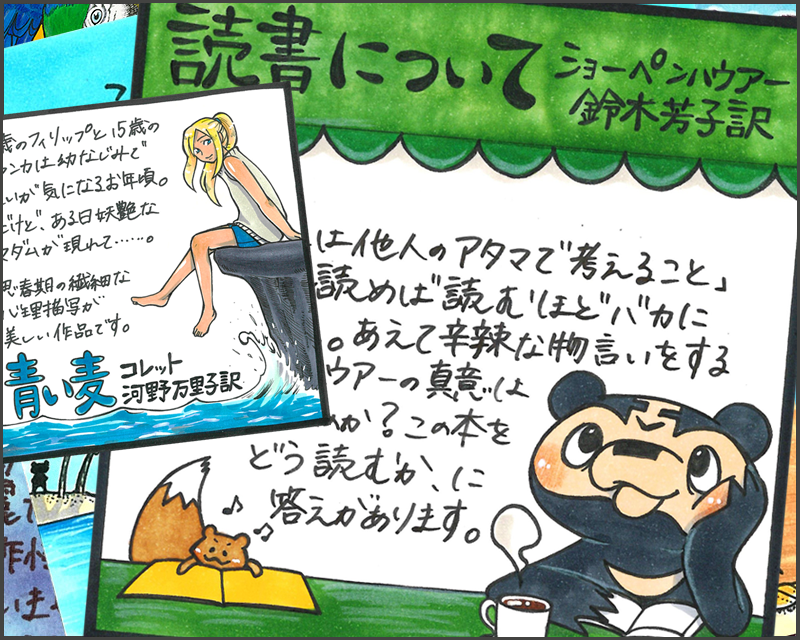いまこそ心に響く、 人間・孔子の言葉
推薦!鹿島茂 (フランス文学者)
「私が敬愛する日本最高の読書人、鶴ヶ谷真一さん訳の『論語』がおもしろくないわけがない」
推薦!岩尾俊兵(経営学者、慶應義塾大学准教授)
「激動の時代こそ二千年変わらない人間の本質を描く『論語』が輝く」
「激動の時代こそ二千年変わらない人間の本質を描く『論語』が輝く」
| 内容 |
|---|
| 日々のいとなみと人間性への理解が簡潔かつなだらかに綴られた、生きる礎としての古典。自由で愛に溢れた孔子の姿が、弟子たちとの厳しくも温かい対話を通して蘇る。世界文学的視点からの注釈と、漢文のリズムを味わう本文構成により、古今東西、愛されてきた『論語』に出会える。 |
| 作品 |
|---|
| 孔子は相手のときどきの心情を手にとるように察する明敏な対談者であった。(中略) 師と弟子とのあいだには、ささやかな心理的ドラマが生まれたことになる。 (「訳者あとがき」より) |
現代語訳 + 読み下し文 + 漢文(返り点つき) + 訳注・補注『論語』がより身近になる「生きるヒントとなる索引」と「人名・語句索引」付き! |
| 目次 |
|---|
| 訳者まえがき――古典の森へ |
| 第一巻 |
| 第一 学而篇 |
| 第二 為政篇 |
| *補注その1 学ぶという喜び |
| 第二巻 |
| 第三 八佾篇 |
| 第四 里仁篇 |
| *補注その2 孔子の個人主義 |
| 第三巻 |
| 第五 公冶長篇 |
| 第六 雍也篇 |
| *補注その3 論語という書物の成立過程 |
| 第四巻 |
| 第七 述而篇 |
| 第八 泰伯篇 |
| *補注その4 仁の成立 |
| 第五巻 |
| 第九 子罕篇 |
| 第十 郷党篇 |
| *補注その5 君子とは |
| 第六巻 |
| 第十一 先進篇 |
| 第十二 顔淵篇 |
| *補注その6 E・パウンドの論語英訳 |
| 第七巻 |
| 第十三 子路篇 |
| 第十四 憲問篇 |
| *補注その7 渋沢栄一、論語精神の体現者 |
| 第八巻 |
| 第十五 衛霊公篇 |
| 第十六 季氏篇 |
| *補注その8 礼楽とは何か |
| 第九巻 |
| 第十七 陽貨篇 |
| 第十八 微子篇 |
| *補注その9 度量衡としての音階 |
| 第十巻 |
| 第十九 子張篇 |
| 第二十 堯曰篇 |
| *補注その10 素読の効用 |
| 解 説 鶴ヶ谷真一 |
| 年 譜 |
| 地 図 |
| 訳者あとがき |
| 索 引 |
| 生きるヒントとなる索引 |
| 語句索引 |
| 人名索引 |
| 644〜646ページの地図は、『世界文学大系69 論語 孟子 大学 中庸』(倉石武四郎訳、筑摩書房、一九六八年三月刊) 折り込みの図を参考にし、訳者の判断により孔子の年齢や表記などに変更を施し、編集部で加工・作成したものです。 |
| 『論語』おもな登場人物しおり |
| [ - ] |
| [訳者] 鶴ヶ谷真一 Tsurugaya Shinichi |
|---|
|
1946年東京都生まれ。エッセイスト。早稲田大学文学部卒業。著書に『書を読んで羊を失う』(第48回日本エッセイスト・クラブ賞)『月光に書を読む』『記憶の箱舟 または読書の変容』など多数。訳書に『三酔人経綸問答』『一年有半』(いずれも中江兆民)がある。 |
| 書評 | |
|---|---|
| 2025.09.20 毎日新聞 | 「素読を尽くし学び成した書」(評者:鹿島茂さん) |